


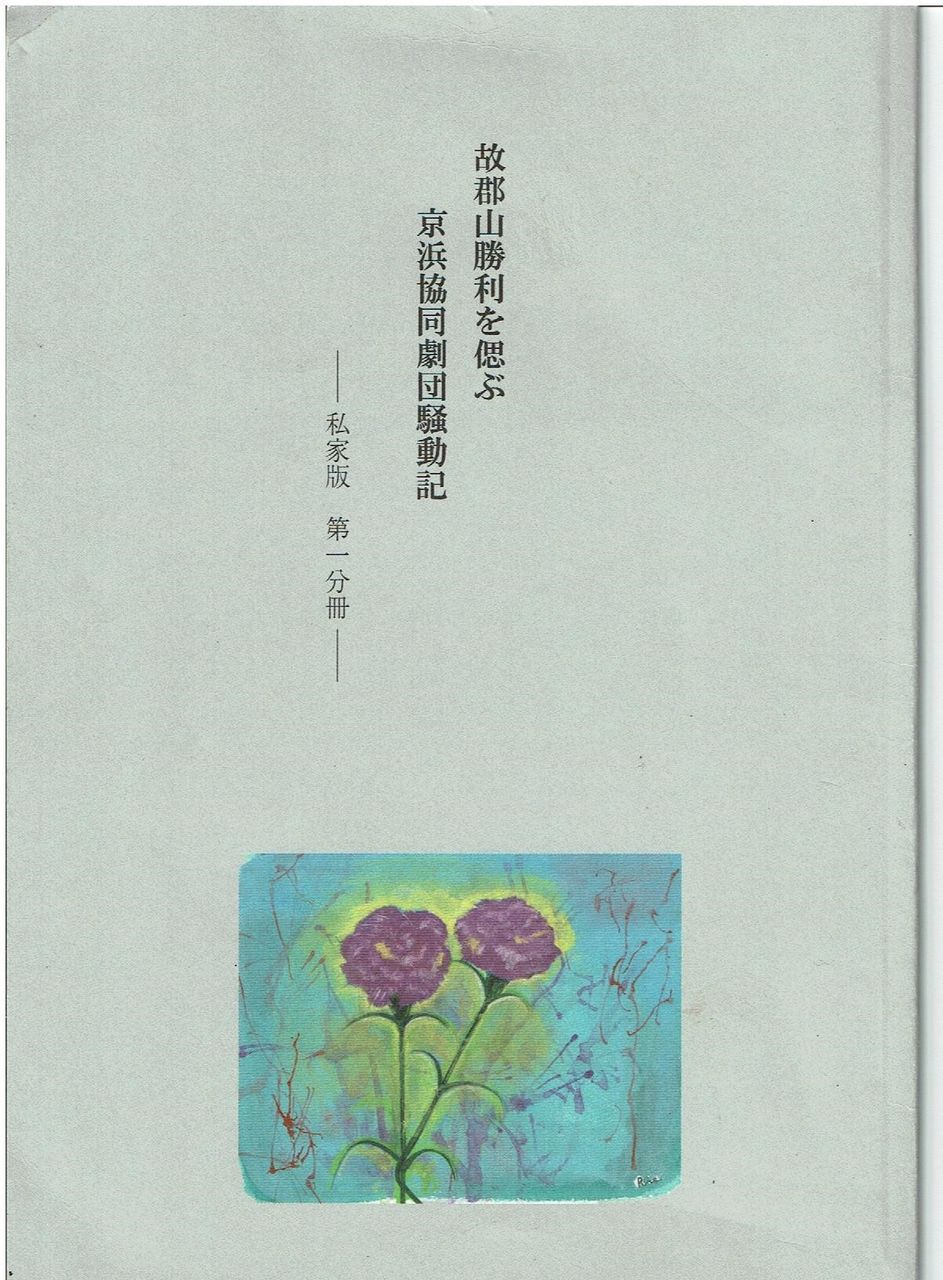
1部 過ぎ去りし日々を問う。
第1章 1950年代という「時代」(その1)
■父の死
小学校の卒業を控えた2月、大雪が降った翌日のことだった。学校から帰った私は、鞄を置いて遊びに出ようとして8畳間に入った(そのころの私は3畳、6畳、8畳に風呂場付きの長屋に7人家族で暮らしており、いちばん広い8畳間は寝室として使われていた)。そこで、私は、父が上半身を起こした姿勢のまま顔を仰向けにのけ反らせた格好で、口から血を吐いているのを見た。私は、それが死を意味していることを直感した。目は、かっと開いたままだった。動転した私は、頭の中が真っ白くなり、後先のことに思いをめぐらす余裕などなく、気がつくと家を飛び出していた。表へ出たもののたったいま目にした光景が頭を離れない。それを振り払おうとして、雪合戦に混ぜて貰ったりしてはみたもの、心中は気が気でなかった。しばらくして家へ戻り、おそるおそる8畳間をのぞいたところ、そこには母がいた。「おとうちゃんが死んじゃった。K先生を呼んできておくれ」という。少々のことでは動じた姿を見せたことがない母だったが、このときばかりは、なにをどうしたらいいのかわからないほどうろたえていた。
私は、K医院まで走った。出てきた医師に、父が死にそうであることを息せき切って話し、すぐに往診にきてほしい旨を訴えた。訴えながら、涙が出るのを抑えられなかった。私の訴えを聞き終えた医師は、顔色ひとつ変えずに、住所を尋ね、往診することを約束してくれた。こどもが涙ながらに人ひとりが死にそうだと訴えているのに、冷たい、と私は思った。
型どおりの診察を終えた医者は、胃出血による心不全という診断を下し、死亡診断書を書くから取りにくるようにといった。*1
*1 父の系統は、弟が胃の病で30代で亡くなっている。兄は、ずっとあとに胃ガンと診断されたが、手術してから5年といわれたにもかかわらず10年以上も生きていた。私も、どちらかというと胃腸が丈夫なほうではない。胃腸病が遺伝的であるといわれていることを考えると、現在の水準で診断すれば、父の病気が胃ガンだったことに間違いない。失業中で医者にかかると言い出せなかった父を、気の毒だと思う。同時に、このようなかたちで貧困が存在することに対して、敵意を覚える。長生きすることが必ずしもいいことであるとは思わないが、貧しさゆえに治療を受けられなかったことに対して、である。
父は、死ぬ前の2年ほどのあいだ定職がなかった。50年に朝鮮戦争が勃発し、いわゆる朝鮮戦争特需が始まるまでの2年ほどの期間は不況期で、人員整理が頻繁に行われた。49年に失業した父は、親類のEさんに頼み込み、その会社で帳面をつけさせて貰っていたが、この仕事も長続きしなかった。商家の出だから、算盤と帳面はつけられたが、近代的な経理事務ができるというわけではなかった。そういう中途半端な労働力を、身内だからということだけで雇いきれないほどの不況だった。
この時期、母のふたりいた弟うち上の弟は露天商をやっていた。その種の仕事の経験がない人だったが、天性の磊落な性格ではったりをかましているうちに、テキヤ仲間に伍していっぱしに場所の仕切りをやるまでになっていた。母がその叔父に窮状を話し、働く先がないならやってみないかという話になった。商品は、向かいのご隠居が考案したおもちゃである。このご隠居はおもしろい人で、もともとが浅草橋の老舗の紙問屋の跡取りだったが、早々と息子に店を譲り、わが家の向かいにお妾さんと暮らしながらこどものおもちゃをあれこれと考案しては、近所の主婦につくらせ、問屋に卸していた。母もそのひとりだったことのからみで、このご隠居に接触して以来、互いにうまがあうのか昵懇の仲になり、叔父の仕入れ先の1つになっていた。
「あにさん、こんなふうにやるんだよ。」
叔父はそういいながら、ヨーヨーにヒントをえて考案されたおもちゃを手にして、父の前で実演した。そのおもちゃは、小さなゴムのボールにアメゴムの紐を付けたもので、投げるとゴムの弾性で手元に戻ってくる。どこへ投げても手元に戻ってくるのがこの商品のウリであることを父に説明し、ぶんぶんと音をたてて振り回しては、上に放り投げ、斜め後ろに投げては鮮やかな手つきで受けとめる。そうしながら、景気がいい口上を述べ立てる。その全てを、こどもにかえったように楽しそうにやるのである。それらの所作は、脇で眺めていると、つい欲しくなるほど見事なものだった。
父は、叔父について商いに出た。が、半日で戻ってきた。母は、どうして半日で戻ってきたのかとなじった。
「あたしにゃできないよ。」
その言い方は、飼っていたニワトリを絞めて貰ったおりと同じだった。この時期、ニワトリを飼い、たまごを換金させることが流行った。わが家でも近所で成鳥を分けて貰って繁殖を試みたが、雄鳥は1羽いればいいので、不要になった雄鳥は駅前の鶏肉店に持ち込んで処分してもらっていた。精肉にしてもらえるのはありがたいのだが、処分料として半分はとられる。それは馬鹿馬鹿しいからおれにまかせろということで、裏の家の次男坊が名乗り出て、絞めてもらったことがある。
トリ鍋を前にした父は「あたしにゃ食べられない。」といったきり、最後まで箸を付けなかった。そのときと同じだった。私は情けないと思った。そして、憎悪を感じた。*2
*2 父に対するこの感情には、いくつかの布石がある。私は、3年生ころまで父と同じ布団で寝ていた。ある日、私は布団の中で屁を放った。父は、その屁が臭いといって、これみよがしに布団をめくって屁を追いやったことがあった。10歳のこども相手の仕打ちとしては、じつに大人気なかった。いまひとつは、間食にまつわる。失業してぶらぶらしていたあいだ、酒が弱い彼は口寂しかったのか、間食を自分でつくった。家庭科の実習で私が真似た脱脂粉乳入りの芋ようかんは、そのひとつだった。そのほかに干し芋をつくった。自分で芋を買ってきて蒸かし、薄く切ってざるに並べ、庭に面した南側の軒下に干した。そこがいちばん日の当たるところだったが、同時にこどもには容易には手が届かない場所でもあった。干し芋は、乾燥をはじめてしばらくした時期の生乾きの状態のときが柔らかいうえに甘みもあって、いちばんうまい。私は、父がつくるその干し芋を、出来上がる前につまみ食いするのがつねだった。わからないように並べ直して置いたところで、減る量を考えれば、誰が盗んだかは一目瞭然だった。しかし、父は、私の行為だとわかっていても叱らなかった。その干し芋は、彼が食うためにつくっているのであって、家族に分け与えるためのものではなかった。が、そうだからといって、盗み食いをしたといって叱ることはできないことだった。
父にしてみれば、私は可愛気がない子だったにちがいない。母は、長男であるということで、私をほかのきょうだいと差別して扱うことが多かった。たとえば、自分の分のおかずを、ほかのこどもには分けないのに、私にだけは自分は口にしないで分けるといった具合に。父は商家の次男だったから、何事に付けても、長男と差別されて育ったことは想像に難くない。そういう意識が潜在的にあり、長男である私を疎んじたのだとすれば、次男である弟を溺愛したことも含めて、いまの私は一連の父の行為を理解できないことではない。
このころから、父は胃が痛むことを口にしていた。母は、その種の愚痴にいっさい取り合わなかった。私にも、ぶらぶらしている言い訳に聞こえた。医者に通う金がない父は売薬を買ってきて飲んでいた。朝鮮人参がいいと聞いてきたものの、医者にかかる金がない状態では高価な朝鮮人参は買えなかった。本物ではないが、いくらか効き目があるだろうということで、人参をおろして飲んだりもしていた。
収入がない父は、タバコ銭にも事欠いていた。この時期のわが家の収入は、母の内職による稼ぎとタンスの中身の売り食いだったから、父に渡せる金は全くなかった。仕方なく、父は妹のところへいって、小遣い銭をねだってきた。この叔母は、日本橋にあったクリーニング屋に嫁いでおり、父の唯一の理解者だった。叔母に勧められたのか、父は、昔の得意先を尋ねて衣紋描きの仕事を貰ってくることもあった。着物をほどいて洗濯し、染みを抜き、剥げ落ちた柄を補修した。補修にさしいては、顔料を大豆の擦ったものや鴬の糞を水で溶かして使っていた。その顔料を細い絵筆でなぞる作業をする父の姿は、それまでに私が見たことがないものだった。*3
*3 父の実家は、洗張屋をやる前は衣紋描きを生業にしていたらしい。といっても新品を扱うのではなく再生を業としていたようで、祖父の代に蔵前に洗い張りを専業にする店を出し、途中からはクリーニング屋に転じていた。洗張屋に転じる前に家を出ているので、正確にいえば、父は商家の出ではなく職人の子弟だったというほうが正しい。
洗張屋といっても、いまの若い人にはわからないと思う。いまでいうクリーニング屋であるが、客から預かった洗濯物を、染みやほつれなどを補修して、新品同様に再生する洗濯屋であると理解してもらえばいい。戦前の日本人はほとんどが和服を着ており、戦後も50年代の半ばころまでは和服のほうが多数派だった。和服の場合も普段着は家で丸洗いするが、余所行きと称する外出着は、いちど解いて布地にばらしてから洗濯し、それに布海苔をつけて板などに張りつけて乾かすという方法で再生していた。これには一定の技術がいるので専門の業者に出すのである。
ちなみに和服というのはじつによく考えられた衣類で、原則として布を裁つことをしないで縫製する。成長期のこどもの場合には丈が伸びることを考慮に入れて長めに作り、丈をたくし上げて着用する。身長が伸びるのに応じて、たくし上げた分を下ろして着る。袖などに丸みを付けるにもハサミで裁つことはせず、丸みを付けて縫ってから裏返す方法で仕立てる。だから、おとなの着物を解くと六尺以上あり、板に張り付けて干すには長すぎるので、両端に針が付いた直系三㍉ほどの竹のひごを使って布の耳の所に針を刺し、竹のバネの力で布地をぴんとさせる方法で干す。こうしていったん解体して洗濯し、仕立て直すのである。だから、原理的には、布地がすり切れるまで再使用が可能な衣類である。
父が定職をもっていたときでも楽ではなかった家計は、父の死でいっそう苦しくなった。母ひとりの働きでは、5人のこどもを養うのは無理だった。まして、高校に行かせるなどということは、より困難なことだった。
父が50歳で逝ったとき、上の姉は旧制女学校の4年だった。4月には新制高校になるため、高校2年に編入されるところを特別のはからいで同じ高校の給仕に雇って貰い、新制になった定時制高校の4年に編入させて貰った。旧制のままなら、残り1年で卒業するはずであるという配慮がされた結果だった。下の姉は新制中学の3年で新制高校に入学するための準備をしていたが、受験をあきらめた。降って湧いたようにおこなわれた学制の変更だったため校舎が間に合わず、私が住んでいた地区の女生徒は管内の私立の女学校に委託される形入学していた。そこにあった1年だけの別科というコースをとることにしたのである。上の姉とのバランスを考えての苦肉の策だった。その結果、彼女は1年後に就職して家計を助けることになった。
父の死から1年のあいだが、わが家がもっとも苦しかった時期だった。母ひとりの働きでは、食っていくことだけでもおぼつかなかった。毎日がタケノコ生活の連続だった。質屋通いは父が生きていたころもやっていたが、この1年間で、タンスの中にあったものは文字どおり空になった。母は平井にあった公益質屋に通った。質草が流れた場合に売値との差額が出ることがあるが、公益質屋だとその差額を貰えたからである。
父が死んだ翌日、私は、いつものとおり学校にいった。告別式は午後からということだったので、午前中は授業を受け、給食を終えてから午後から早退したい旨を担任に申し出た。話を聞いた彼女は、いたく驚いた様子だった。
担任は私を教壇の前に立たせ、級友に事情を説明すると同時に男の子はこうあるべきであるという意味のことを述べた。私は、この過褒を俯きながら面はゆい思いで聞いた。通夜は身内だけで済ませたし、葬儀の準備といったところでこどもの私にはすることがなかった。父の死は、予想外のことではあったが、だからといってそれまでの日常生活が激変するとは思えなかった。いつもどおりの日常を過ごしたのはそういう思いがあったからで、涙が出なかったのもそのゆえだった。
その涙が、級友が揃って焼香に現れたとき、どっと湧いて出た。努めて冷静であろうと振る舞って堪えていたものが、級友の顔を見てどっと溢れ出るのを止められなかった。感情が、理性とは別のところで働くことを知った最初の機会だった。
この件を機に、担任の私に対する評価は、がらっと変わった。私は、人におもねることができない質の人間である。この性格は、父からも母からも受け継いでおり、とくに目上の人と対するさいに表れた。教師に対しては、在学中はできるかぎり距離をとるという姿勢をとった。この担任の場合もそうで、在学中はいちども訪問しなかったが、卒業してからはしばしば訪ねるようになった。在学中は頻繁に訪ねたこどもたちは、利害がなくなったとたんに訪れなくなっていた。そういう律儀さが貴重だということで、この教師には見直されもした。*4
*4 私には、そうした自分を誇りに思う気持ちがある。それはたんなる不器用がもたらすものにすぎないと考えた時期もあったが、父が逝った歳に近づいてからはどうもそれだけではないと思うようになった。
■新聞配達
小学校の6年ころから、私の課題は新聞配達の株を手に入れることだった。貧しい家のこどもにとって、新聞配達はこどもにできる唯一の稼ぎ口だった。近所で新聞配達をして稼いでいるこどもを指して、母は口癖のように「だれだれさんを見習え」といい、褒めそやした。母にいわれるまでもなく、私は、新聞配達をやりたかった。自分ひとりで全部を使えるとは思っていなかったが、自分で稼いだ金であるからには、少しは自分でも使える可能性があると考えていたからだ。
前任者が後任を指名して権利を譲渡するという意味でいえば、配達員の口は、一種の株であるといえた。誰かが辞めるまでは空きがなく、辞めたあとの株を譲って貰える関係がない限り、やりたいという希望だけでは仕事にあり就けないのである。
この株には実入りと仕事の軽重によって、かなり厳密な序列があった。私が株を手に入れた毎日新聞を例にとると、駅前の立ち売りから始まり夕刊の配達、朝刊の配達、集金の順に、あとになるほど高位になる位階制があった。上のほうから順に報酬が高いことが決め手だが、同じ新聞配達でも駅の近くや住宅の密集地は効率が良いために短時間で済み、序列が上にランクされた。当時の中学生は大半が卒業と同時に就職したので、3年生が卒業する時期になると空きができた。空きが出ると、よりよいポストを譲って貰ったものが自分の株を親しい希望者に譲渡するのである。*5
*5 それは、きわめて閉鎖的で陰湿な、縁故関係だけが貫かれる狭い社会だった。たとえば、私と同級のKの場合は、兄から双子の弟たちに、その双子の兄弟から下の弟へと株を委譲しており、ざっと数えただけでも6、7年間はこの貴重な株を独占しつづけていた。私が夕刊から朝刊の株を譲り受けたNは、譲渡にさいして中学1年になった弟に私の夕刊の株を譲ることを条件にした。
新聞の輸送は、電車の最後尾に貨物車が1両だけ連結されていて、定時になると駅にとりにいく方法で行われていた。電車が駅に着くと新聞の束がホームに放り投げられる。その中から自分の専売所宛の梱包を拾い上げ、リアカーに載せて運んでくるのである。それは専従の配達員の仕事だった。やれる気があればひとりでできない仕事ではなかったが、複数の人間がやるほうが能率的だった。で、手伝うといくらかの報酬がもらえた。朝刊の場合、一番電車で運ばれてくるのをとりにいくためには30分は早く専売所へ顔を出さなければならない。しかし、早朝の30分は遊び盛りの少年たちにとって少々の金には換えられなかった。彼らはすでに収入を確保していたうえに、やればひとりでやれないことはない作業である。1人分報酬を数人で分ければ貰える報酬は高がしれている。だから、この仕事だけは株の対象にはならず、希望すれば誰でも手にすることができ、希望者は少なかった。
毎日新聞の販売所は、京成線の国府台駅前に店頭売りの株をもっていた。その株を、同じクラスのMは誰かから譲り受けていた。卒業を控えて配達の株が空き、Mは夕刊の配達の口を手に入れることができたので、前から口をかけていたその株を私に譲ってくれた。こうして、私は念願の稼ぎ口を手に入れた。
駅前の立ち売りの株を手に入れた私は、夕刊が着く時間を見計らって専売所にいった。この仕事の責任者である店主の長男から持っていく商品を受け取ると、自転車の荷台にくくりつけ、国道を30分ほどかけて国府台駅まで走った。駅前には交番があり、その脇に販売用の机を置かせて貰っていた。それを組み立て、商品を並べる。7時半が店を仕舞うメドとして与えられていた。その一方で「内外タイムス」の売り切れを1つのメドとするようにもいわれていた。*6
*6 夕刊紙としてスタートした「内外タイムス」は宅配がなく、全てを駅売りに依拠する最初の新聞だった。週刊誌も新聞社系のものだけしかなく、持っていった「内外タイムス」の売り切れはそれ以上は売上が見込めない時間帯に入ったことを意味していた。
7時半に店を畳むと専売所への帰着は8時を回ることになる。売上を精算して家に帰れるのは早くても8時半、少し遅くなると9時に限りなく近くなった。夕刊がない日曜日と大雨の日だけが唯一の休みという過酷な条件、それが駅売りの仕事だった。それでいて報酬は歩合制だったので、配達のほうが歩がよかった。珍しく「内外タイムス」が7時前に売り切れたことがあり、私は店を畳んで専売所に戻ったことがある。いつもなら8時を回るところを、早々と店を畳む時間に戻ってきた私は、店主の次男に理由を尋ねられた。私は「内外が売り切れたから。」と答えた。誰がそんなこといったかと問う次男に、私はこの仕事の責任者である長男の名を挙げた。
「○○さんがそういったのか。」と困った人だという表情を露わにし、しかし、ややあって「内外の売り切れは1つの目安であり、原則は7時半が店仕舞いであること」を私にきっぱりと宣言した。その表情には、遊び好きで経営者に不向きな兄に遠慮しつつも、自分が支えないことにはこの店が維持できないという彼の決意がこもっていた。こうして私は、「内外タイムス」の売り切れは1つの目安であって、売り切れたからといって即店を畳んでもよいということではないことを知らされた。1日も早く配達の株を手に入れたいという気分が募った。
年が明け、3月になって夕刊の株が空くことになった。その株を確保できた私は、ほっとした。卒業する3年生の朝刊の株を手に入れることができたMが夕刊の株を私に譲ってくれたのである。配達地域は、専売所からもっとも離れていた。郊外の農村の名残りが濃厚なその地域は、家の数はまばらで、やたらと広い配達地域だった。最初の1軒目を配達するまでに店を出てから4㌔近く歩かなければならず、配達を終えるまでには1時間以上かかった。それでも、寒い風に吹きさらされる立ち売りの退屈さに比べると、からだを動かしつづけているうちに仕事が終わってしまうので気分的には比較にならいほど楽な仕事だった。
苦労して確保した収入だったが、報酬をもらうと私はそのままそっくり母に渡した。期待していた自由になる金が増えることはなかった。それまで口癖のように「○○くんはえらい。」といっていた母の嫌みな言辞はやんだ。が、だからといって、その新聞配達をやり始めた私が褒められることはなかった。正確なことはおぼえていない。しかし、駅前にあった古本屋でしょっちゅう本を買っていたことを考えると、小遣いは私の稼ぎからいくらかは出ていたにちがいない。こうして私の中学時代は終わった。
■衣食住供与プラス報酬付きの魅力
わが家の経済状態からいって、私は昼間の高校へ行くつもりはなかった。だから、できることなら働きながら勉強もできる機会があればと考えていた。少年自衛官という制度があり、衣食住の全てが保証されたうえで、高卒の資格もとれるという触れ込みだった。願ってもない好条件である。本気でこれに応募しようと考えた私は、願書を貰うために隊員が常駐している区役所の支所に出向いた。
けっして扇動したわけではなかったし、そのつもりもなかった。しかし、結果として見れば、それは優れたアジテーションになってしまった。少年自衛官という制度があること、試験はやや難しいがある程度の水準なら十分に合格できること、そしてなによりも衣食住が保証されたうえに報酬と高校卒の資格を得られることが決め手だった。最後の条件が最大の扇動材料であり、私のオルグが優れていたわけではない。なぜというに、私はひとりの級友にそういう制度があり、自分はそれに応募するつもりであること告げたほかには、なにもしなかったからだ。
その級友がもうひとりの級友に耳打ちし、それを聞いた級友がまた別の級友に告げるといった形で、この円環はクラスの枠を越える広がりを見せる1つ手前のところで教師に耳に届いた。あとで知ったことだが、教員組合はもとよりPTAまで巻き込む騒動になっていた。
担任に呼ばれた私は、事情はよくわかるし心情もわかる。しかし、兵隊になるということは戦争に加担することにほかならない。事情はどうあれ、ほかの道がないわけではない、と説得される羽目に陥った。担任の話では、私を可愛がってくれていたふたりの教師が説得に乗り出してもいいといっているという。ともに学徒出陣で駆り出された口で、うちひとりは腰に受けた貫通銃傷の後遺症のため、やや引きずり気味に歩いていた。必要なら親を説得するとまでいわれると、私にはそれを押してまで応募する気にはなれず、あっさりと彼女の説得に応じることにした。気分としてはすっきりはしなかったものの、もともとが兵隊になりたくて思いついたものではない。そうした周囲の反対を押しても意地を張る必要を感じなかった。
定時制にいくことも考えた。この考えは、上の姉に反対された。姉は、なんとかするから昼間の学校へ行けといい、母もそれに同調した。
そこで、受験の対象は実業高校に絞られた。数字をいじくることが苦手なうえに客あしらいが全くできないということは実証済みだったので、商業高校はあらかじめ除外した。受験雑誌で調べてみると、都立の農業高校が2つあることがわかった。世田谷にある園芸高校では、当時はまだ珍しかったトラクターを使った実習を行っているということだった。級友には農家の子弟がおり、その仕事ぶりは私にとって日常の範囲にあった。効率は悪いし、収入もいいとはいえない。なによりもわが家には農地がない。彼らの親がやっている農業とは異なる「新しい農業」なら、企業の従業員として働くことが可能だというころに、私は魅力を感じた。が、いかんせん通学に要する時間を考えると、乗り気にはなれなかった。もう1つは近くの亀有にあったが、創立から日が浅く校舎を建設中だったこともあって、はじめから検討する対象にしなかった。
こうした引き算をするなかで、工業高校でも数学が必須でない学科があることに気づき、水道橋にある工芸高校の図案科か木工科に的を絞ることにした。 この時期の私には、ふたりのごく親密な友人がいた。IとNである。ふたりとも迷うことなくすでに自分の進路を決めていた。Iは商業高校、Nは工業高校の機械科だった。年が明け、私はNとふたりして見学に行くことにした。Nの本命は工芸高校だったが、ついでに蔵前にある蔵前工業も覗いてみたいという。同じ沿線にあるので、途中下車していくことに決めた。*7
*7 蔵前工業高校は、東京工業大学が同じ名前を名乗っていたことから、同じ学校であると錯覚する人が多かったが、じつは別の学校である。しかし、全く別かというとそうでもなく、敷地は旧蔵前工業のものを使っていた。そのことに象徴されるように中堅技術者の養成校としては高い水準を保持していた。生徒も優秀なものが多く集まり、競争率は高かった。
私たちは、近いほうから訪問することに決め、はじめに蔵前工業を訪ねた。私たちの中学は分校から独立した学校であるために、先輩がひとりもいない。仕方なく、私たちはなんのつてもなしに訪問先を訪ねることにし、守衛室で用向きを伝えた。その種の見学者は滅多にないようで、守衛が教員室に電話をかけ、しばらく待たされた。30分は待たされただろうか、生徒会長が現れ案内するという。詰め襟の学生服を着た生徒会長は、対応も含めていかにも優等生らしい印象を私たちに与えた。それに反して、つづいて訪れた工芸高校では、全てがちがっていた。私たちの用向きを聞いた守衛は、勝手に見て行けという。案内してくれる人がないまま、私たちは遠慮がちに教室を覗いて歩き、一回りしたところで屋上に出た。そこで私たちは見たのである。実習用のつなぎを着た生徒が数人、タバコをふかしているのを。私は、その光景を見てこの学校がすっかり気に入った。Nも同感だったようで、帰りの電車のなかでは「あれはいいや」といいながら、しきりにたばこを吹かす仕草をしては陽気にはしゃいでいた。
翌日になり、学校へ行ったNは、屋上でタバコとふかしている先輩がいる「すごく気に入った高校」を、級友に向かって宣伝して回った。
商業デザインか木工をやるつもりでいた私は、ここでもまた志望先を変えることになった。私には、色神検査をおこなうと「赤緑色弱」と判定される障害があった。信号も絵の具も区別できるのに、その検査をやると「色神異常」と判定されるのだ。このことを気にした姉が知人のデザイナーに相談したところ、就職のさいに不利であるから考え直したほうがよいとのことだった。商業デザインは色感が問われる。木工なら問題はないだろうとは思った。が、稼ぐために行く高校である。就職ができないとなると、考え直さざるをえなかった。担任に「先行きどうにでもつぶしが利くから普通高校へいってみたほうがいい」といわれると、「それもそうかな」という気分になった。
■奨学金、バイトに継ぐバイト
20歳に満たない女ふたりと格別な技能をもたない中年の寡婦、この3人がわが家の収入源である。それぞれの食い扶持は自前で賄えるとして、3人のこどもを養うためには残余がなければならない。が、ほかにこれといった収入はない。支出を極端に抑えないことにはやっていけない。そういう条件にあって、働かせれば己の食い扶持程度は稼ぐだろう私を進学させるという彼女たちの判断は、先のあてがあってのものではなかった。いま考えるとどうやって私たち3人を食わせていたのかと思うが、それでも新聞はとっていた。父も新聞を読むのが好きだったが、尋常小学校の課程を4年しか終えてない母も、新聞は毎日目を通していた。
入学直後のホームルームで、学校からの諸注意が担任からあった。そのおりに、ついでのように「奨学金を貰いたいものは手を挙げろ。」と担任が事務的にいった。「そういう手があるのか」と私は思った。教室を出る担任の跡を追うようにして教員室にいき、奨学金を受けたい旨を申し出た。「そうか。」といっただけで委細を問うことなく、担任は申請に必要な書類を取り出し、必要事項を書き込んで持ってくるようにいった。申請書は自分で勝手に書いて提出した。これで学費と定期代が賄えることになった。
しばらくして全校一斉のテストがおこなわれた。進学志望のものは知っていたようだが、私はそのテストがなんのためにおこなわれるのかを知らなかった。英語も数学も、全く習っていない問題が出題されていたのにはいささか奇異な感じがした。が、不意打ちテストはお手のものだと思っていた私は、どの程度の力があるのかを確かめるためのものだろうと考えた。しかし、採点が戻ってきて、得意の国語が30点だったのにはショックを受けた。それまでにそういう点数をとったことがなかったからだ。『徒然草』からの出題だったか「高名な木登り」という句があり、私はそれを人の姓だと思って読み、その設問には答えられなかった。いま考えれば、「高名な」とあるからには、形容詞であって名詞ではないので、誤読することはないはずだが、人1倍乱読していたわりには国語力は低かったものと思われる。
このテストは、1年から3年までの全生徒が同じ問題に挑戦する国立大学受験のための(そのためだけにおこなわれる)模擬試験だった。試験結果は、採点後に得点順に50位までが一覧にして張り出される。この一覧が「番付表」と呼ばれてこともあとで知った。この番付にのれば国立大学はok。20位以内なら現役で東大合格間違いないというのがもっぱらの噂だった。なかには優秀なのがいて、上級生に伍して上位に食い込むのがいる。この連中の追い上げ効果を期待してのテストだった。
そのからくりを知ってからの私にとって、年に3回おこなわれるこのテスト期間中は、絶好の稼ぎ時になった。国立大学受験を前提にしているために、同じ条件の日程が組まれていたから、あらかじめ私立を受験するものは自分の受験教科だけしか受ける必要がない。学校もそのこと知っており、出欠をとらないので、試験中は休んでも出席扱いにされた。かくして、夏、冬、春の休みに加えて、このテスト期間中の私はアルバイトに精を出すことになった。
アルバイトの斡旋は、千鳥ヶ淵の近衛第1連隊の跡地にあった学徒援護会という組織だけが、おこなっていた。対象は主に学生だったが、生徒も高校生なら認められた。そのことは入学前にIの姉から聞いて知っていたので、私は在学中の3年間、休みとなると斡旋を受けて働いた。学生が対象の仕事はかなりあったが、高校生を対象とする求人は限られていた。数少ない「高校生も可」とある求人票を探し出しては、どんな仕事でもやった。対象が「高校生」とある求人票を見つけたときには、幸福感で豊かな気分になれた。登録している高校生は限られており(おそらく私のほかにはいたとしても数名だったと思う。)、「高校生」と限定された募集なら即斡旋されることがわかっていたからだった。
彫刻家のモデルの仕事だった。柔道2段を誇る大男のラグビー部の先輩は、私の貧弱な肉体をしげしげと眺めながら「おまえがモデルかよ。」といい、あきれたのようにつぶやいたが、雇い主である彫刻家の目的はまだ青年になりきっていない少年像の制作だった。報酬は日当で貰える工場の作業に比べて安かったが、3カ月つづくという条件が魅力だった。このようにして得た金だけが、私が自由に使える金だった。
いまでは2つとも死語になってしまったようだが、鉄道の不正乗車のことをキセルまたは薩摩之守といった*8。私は、このキセルをやって捕まったことが2度ある。
*8 キセルは煙管とも書く喫煙具。吸い口と材料を詰める箇所が金属で、煙を通す部分が金属製であることから、入場と退場だけに金(属)を使い中間には金(属)を使わない不正乗車のことを指していう。薩摩之守は平忠度(ただのり)の官名が薩摩之守だったことに由来している。
はじめはもっとも親しかったOが腎炎で倒れ、休学して療養していたのを見舞ったおりのことである。期末試験が終わり、ひと息ついたという気分もあって、たまたま帰りの電車の中で一緒になったTと見舞いに行こうということになった。Oの家は私の下車駅の2つ先にあり、Tの下車駅と同じだった。上級生から学帽に定期乗車券を入れて受け渡しするキセルの方法を聞いていた私は、Tにその方法を提案した。私に当時の最低乗車区間の料金だった10円がなかったわけではない。このときは、半分は遊び気分での不正乗車だったのである。
私の提案に気楽な気分で同意したTから、定期券を受け取ったまではよかった。が、なにげなくやったつもりがあまりにも公然とやったので、駅員が見逃さかった。改札口で捕まり、事務室に連れて行かれ、絞られる羽目になった。定期券を手になまえを尋ねる駅員に、私はTの姓名を名乗った。改札の外から事務室の様子を覗き見ているTの心配そうな顔が窓越しに見える。「嘘をついてもダメだ。あそこで覗いているのがTだろう。」そう図星を指され、私は観念した。
「○○高校といえば模範になって貰わなければならない学校じゃないか。」そういう学校の生徒不正をしてもいいのか。恥ずかしくはないのか。等々と駅員は説教をたれる。こういうときには、低姿勢に徹することが必須であることを知らされていた私は、もっぱら頭を下げつづけた。通常なら3倍の罰則料金を払わなければならないところだが「きょうのところ格別に許す。」ということばが駅員の口から出るまでに小1時間かかり、やっとのことで解放された。
私たちの話を聞いたOの母親は、薩摩之守程度でそんなに絞り上げるのはけしからんという。話し込んでいるうちに帰宅したOの父親も、選良候補生のいたずらに駅員ごときがその劣等意識でいびるなど不届きだといい、冗談交じりに駅長に抗議するかという。モラトリアム期間にありがちなこの種の「不良行為」は、社会が許容する範囲内にあったのである。
2度めの不正乗車、これは意図的だった。夏休みにやったバイトのおりのことである。仕事は工事現場の廃材を片付ける作業で、銀座の現場に行かされた。2週間ほどの期間だったので、新橋駅発行の最低料金の回数券を買い、仕事を終えてから有楽町で乗り、通学定期で下車。翌日はその回数券を使って新橋で降りるという方法で、途中をキセルするだけでなく、1枚の回数券を2回使ったのである。正規に払う料金とキセルによって確保できる金額との差は、当時の私には大きかったのである。
無事だったのは数回で目ざとい駅員に呼び止められ、役務室に連れて行かれ、主任格の駅員に渡された。捕まるはずがないと思っていた私に、その駅員にこの種の不正乗車が典型的なものであることを説明され、私は観念した。学帽にジャンパー、高下駄を履いたどう見ても貧しい私の姿にかつての己を見たのか、駅員は同情的だった。家の事情を聞き、「気持ちはわかる。わかるが規則だから守って貰わなければならない。」といい、精算所で精算をすることを告げられた。3倍の罰則料金を払うように、とはいわれなかった。
■間違えて入ってきた生徒
通称「ドロ健」と私たちが読んでいた数学の教師がいた。女生徒の中には、1次志望に落ちて2次志望で入学してきた人がいる。勢い成績が落ちるのは否めないわけだが、そういう生徒を目ざとく見つけてはねちねちと質問を浴びせて立ち往生させ「おまえ、間違えて入ってきたんじゃないか。」と口汚く罵倒するのである。別の意味で間違えて入ってしまった私は、自分のことをいわれているようで、たまらない思いがし、好きになれない教師だった。
2学期の初日の教室には、立ち往生させられた女生徒ともうひとりAの席が空席になっていた。代わりに教室の後ろにふたりの見知らぬ顔があった。担任から転入生であることが告げられ、両名は空いた席に座るようにいわれた。授業に付いていけない生徒は追放され、代わって優秀な生徒で補充する。これがこの学校がとっていた「水準を維持するための方式」だった。文芸クラブで一緒だったSさんもそのうちのひとりだったようで、いつの間にか姿を見せなくなっていた。
卒業アルバムを見ると、痩せこけた私は洗いざらしの木綿の学生服姿で写っている。別のアルバムにある春の遠足ではそれがサージの服に替わっていることから推して、中学のときのものを進学後もしばらくは着ていたのだと思う。西部は、高校時代にオーバーコートを持っていなかったことをもって貧しさをことさらのように強調している。が、それは「うちはそんなに貧乏ではなかった」と「文句をいう」彼の妹たち(『友情』p22・23)のほうが正しい。好意的に解釈したとしても、西部の「貧しかったという思い込み」による錯覚にほかならない。この時代の平均的な庶民は、家族が1つ屋根の下で肩を寄せ合ってガマン比べのような協同をしないかぎりは生きてはいけなかった。貧しかったとはいえ私の場合は中の下あたりで、下に属する人たちはもっとたくさんいたし、だいたいが年子を揃って大学にやれる家庭など、東京でも上に属さないかぎり不可能な時代だった。
そうはいっても、私の高校生活は充実していた。在校生の9割までが進学志望であるなかで、いま考えると、経済的な事情から進学が難しい級友の多くは暗い表情をしていたように思う。しかし、暗い表情をしていたのは彼らだけでなく、周囲の期待に応えなくてはならない連中も暗い顔をしていたから、親しい関係でないかぎり外から見たかぎり両者は区別がつかなかった。そういう連中に比べて、あらかじめ進学する気がない私は気楽だった。入学した当初は文系のクラブ3つ、運動部も3つのクラブに加入を申し出た。水泳部は夏だけだからやれないことはなかっただろうが、ラグビー部と柔道部の掛け持ち無理。生物部はおもしろくなさそうなのでやめ、運動部はラグビー1つに絞り、新聞部と文芸(どういうわけか文芸部といわず文学部と称していた)部に所属することにした。新聞は季刊、同人誌は年に2回の発刊だったから時間のやりくりがついたので、両方で中心的な役割を果たしていた。かくして「間違えて入ってきた生徒」の3年間の高校生活が始まった。
■政治的後進地
新聞部は生徒会役員室と同居していた。小学5年から学級新聞をつくっていた私は、当然のことのように新聞つくりにたずさわることになった。
ある元過激派の手記
――過ぎ去りし日々を問う。
■この手記を書くに至った経緯と理由
なぜ、予定していた計画を変更してまでこの手記を書くことに至ったか。まずは、その経緯と理由から書く。
昨年の後半は、ひょんなことから西部との対峙をすることになった(その経緯と中身については別掲のノートあるので省く)。西部との対峙に一段落を着けたとはいえ、荒稿を書き終えてから3年もたっている。中断していた「光りと陰」の次稿にとりかかるには、それなりの準備が必要になる。それでも、ふた月もあれば、なんとか冒頭の書き出し程度なら書けるという自信があった。荒稿を虫干ししていた3年のあいだに、それなりの構想を詰めていたからだ。
気分転換に映画を観たりして、いざレジュメに取りかかろうとしていたおりである。突然、旧友のFから電話がかかってきた。高校時代の同級生であるTと連絡をとりたいと思い、だいぶ前に会ったおりにFがTの所在を知っていると聞いていたので、Fの線をたどってTと連絡をとった。連絡がとれたことについてはメールで知らせてあり、用件は済んでいた。いまのところ、Fと私のあいだにはそれから先の接点はない。だから、向こうから電話があるとは思っていなかったのである。
久しぶりだから声でも聞かせようということなのかと思いながら電話口で応対した私に、Fはとてつもないことを口にした。本多さんを殺した直後に革マルの根本から小野田襄二に電話があったこと。根本が「本多暗殺で革マルからの殺しは打ち止めにする。30人程度の犠牲者は覚悟している。二カ月間、組織討論して決定したことだ。」といったことが、小野田が書いた本に書かれているというのだ。
生来が私は群れることを好まない。正確にいえば、群れることに伴う馴れ合いに対して、生理的・気分的に好きになれない質なのだ。そういう私が、もっとも閉鎖的な過激派組織の一員になった経緯については、おいおい書くことにするが、ひとことでいえば、本多延嘉という人物に魅せられてしまったことが原因である。歴史に「もし」はないことだが、もし本多さんに会うことがなかったなら、私は過激派にはなったかもしれないが、当人からじかに口説かれることがなかったとしたら、その組織成員にならなかっただろうことだけは断言できる。そういう私だったから、組織を離れてからも群れることはしてこなかった。1度だけ乞われて全共闘の総括をするための組織つくりに参画したことはある。が、そのおりも、いいだしっぺのMに、「腐れ縁だから付き合うが、1年だけだよ」と念を押し、活動は1年に限るという会則をつくり、1年たった時点で解散した。その1年ほどのあいだ、元過激派と称する連中が書いたものに目を通してみたが、どれもこれもいい加減で、まともなものは鈴木貞美が書いたもののみ。それ以外には読むに耐えるものにお目にかかることはなかった。
以来、私は、その類のものに目を通すことをやめた。西部の『60年安保』に目を通していなかった(あること自体を知らなかった)のは、上に述べたような経緯による。当然ことながら、Fが指摘した小野田の本についても、読んでいなかったし、そういうものがあること自体を知らなかった。しかし、Fが吐いたことは、ことの次元が異なっていた。普通なら活字にできる中身ではない。活字にするということは、のちのちまで残ることを意味している。話の中身からして、小野田が活字にすることを期待して、根本がいったものではないことは明かだ。そういう中身を、ここにきて明らかにするとなれば、小野田にそれなりの決意があってのことである。私は半分以上うわの空で、長電話になったFの声を電話越しに聞き流していた。生返事をしながら、私は頭の中ではどう考えたらよいかだけを考えていた。
電話を切ったあと、私は、問題の本をネットで注文した。1日おいて、本が届き、その日のうちに読み終えた。
問題の箇所で小野田は次のように書いていた。
《はたして、公表していいことなのか、迷いに迷った末のことから話したい。
革命的共産主義者同盟(革共同)書記長本多延嘉が革マルに殺されたのは、一九七五年三月一四日である。十日ほど経ってのこと、革マルの根本仁から電話があった。「小野田、どう思うか」。ぼくは声が出なかった。続いて、「これによって多数の死者が出ることになるが、革マルからの殺しは本多書記長をもって打ち止めにする。二カ月間、組織討論して決定したことだ」。ぼくは根本の言葉に圧倒されていた。非情の美しさを感じもした。》
「30人程度」といった部分が「多数」となっているほかは、Fのことばのとおりのことが書かれていた。「30人程度」と「多数」にさしたるちがいはないとしがちだが、受け取る側からすれば、ことばがもつ意味合いにかなりの差がある。30という数詞と多数という代名詞のちがいである。Fが「多数」とあるところを勝手に「30」と思い込んで私に話したのか、それとも情報通のFが別の回路から仕入れたものなのか、いずれにせよこの話は実際に両者のあいだで交わされたものにちがいない、と私は判断した。そして、私は慄然たる思いに襲われた。
問題は、根本が予測する「多数の死者」の中に自分を入れていないことにある。2カ月かけたという組織討論に参画したであろうもの(当然のことながらごくごく限られた数だ)も、その数には入っていない。殺されるのは、そういう討議に参加していない(あらかじめ閉め出されている)下部の組織成員なのだ。ごく限られた(おそらく10指に満たない)人間が、彼らを指導者として信じている下部の組織成員の生死を、彼らのあずかり知らないところで決め、組織外の人間に対して話す――そういう恐ろしい組織を、私もその一端を担っていた過激派組織が生み出していたことに対して、このままで黙っているわけにはいかなくなった。と同時に、同じような心境から書いたと思われる小野田が、この根本の発言に「非情の美しさを感じもした」と書いていることに対して激しい憤りをおぼえた。中身のすさまじさに「圧倒され」るのは仕方がないとして、これほど非道な言辞を浴びせかけられて「非情の美しさ」を感じる精神のありようが、私には理解できなかった。
《【限りなく虚しい殺し】――新左翼(革共同)の負の遺産はあまりに大きい。ぼくが語らなければ永遠に葬り去られる事実(ぼくの責任も含めて)を語ろうと思う。――》
引用は、問題の本『革命的左翼という擬制』の「序にかえて」のむすびに記されている小野田の心情である。その心情は是とするものの、同書は、還暦を過ぎて書いたものとしてはお粗末極まりなかった。だから、これ以上は付き合う必要がないと思った。しかし、「ままよ」と考え直し、念のために同書で小野田が言及している過去に彼が書いた文書を読んでみることにした。判断するのは読んだあとにすればいい、と思い直したのだ。年の功である。10年、いや5年前だったとしても、いままでの私なら、この種の煩わしさは避けたと思う。いまの私は、その類の傲岸さがなくなってきている。
問題の文書が掲載されている小冊子は、数日後に小野田がやっている書店から郵送されてきた。肝心なところで問題を含んでいるとはいえ、こちらのほうがまともだったのには驚いた。小野田は私と1歳しかちがわない。ボケるには早すぎる歳でもある。麒麟も歳をとると駄馬と化す好例なのかもしれない。矛盾する言い方だが、肝心なところで的を射ている。わが身に照らして、考えさせられる箇所を多く含んでいる。慎重を期したことが吉と出たといってよい。
そうであるからには、予定を変更して小野田に付き合わざるをえない。
どこの、どれが、どうお粗末なのか、どの部分の、なにが、どのように正鵠なのかについて書くには、いましばらくの準備が必要だ。準備不足のいま、それらについてはおいおい書くことにして、以下、小野田が提起している問題の核心だと思うことについてふれ、この手記の序にかえたい。
■一無名党員とレーニン
ゲ・イ・ミャスニコフ。1989年生れのロシア共産党員である。ただし、私がこの人物について知っているのは、レーニン全集の巻末に記されている簡単な略歴とレーニンが書いた彼宛の公開書簡のみであり、ほかのことはなにも知らない。あとに述べるような理由から、永久にわからないだろう人物、いってみれば、20世紀前半のロシアに生きた多くの革命家のひとりである。まずは、巻末の略歴を見てみよう。
《ミャスニコフ、ゲ・イ(1989年生)――共産党員、労働者出身。1906年から革命運動に参加し、逮捕、追放、逃亡をくりかえす。第3および第4回全ロシア・ソヴェト大会のぺルミ県代表。1920年、ベトログラードに派遣されたが、翌年5月、党中央委員会に「報告書」を提出して、党ペトログラード組織の欠陥なるものを強調、民主主義的自由の欠如がその原因であるとしてあらゆる政治的流派にたいする言論・出版の自由を要求、さらに同年7月、論文『焦眉の問題』を発表して、さきの要求を固執した。党中央委員会組織局が8月22日の決定で、彼の要求は党の利益に反するとみとめたのちにも、ぺルミ県で党中央の政策に反対する煽動をおこなって党から除名された。のち反党集団「労働者グループ」の指導者。》
この略歴からわかるのは次のことである。
① 1906年から革命運動に参加し、逮捕、追放、逃亡をくりかえした――
1960年といえば、前年に第1次ロシア革命が勃発した翌年のことである。16歳でその現実にふれたミャスニコフは、翌年に17歳で革命運動に身を投じたことになるが、ロシア社会民主党は03年の第2回大会でレーニン派(ボリシェビキ)とプレハノフ派(メニシェビキ)に分裂していることを考えると、革命前にボリシェビキに参画した歴としたボリシェビキだと判断してよいと思われるただし、両者の最終的な分裂は12年なので、わずかではあるが疑問の余地はある。しかし、このことも、ミャスニコフがボリシェビキが権力を奪取した17年革命の前後に参画したボリシェビキであれば、そのことに言及しているはずである。その言及がされていないことから推して、私の判断はまちがっていないと思う。ここでもう1つおさえておく必要があることは、ミャスニコフが労働者出身であるということである。この時期の革命家は例外なく知識階層の出身である。ちなみに、およそ知性のかけらすら感じさせないスターリンですら、貧困層の出身であったとはいえ「神学生」だった。生粋の労働者出身の革命家は、存在そのものが珍しい。
② ミャスニコフは、2つの文書を書いている――
略歴で「報告書」と論文『焦眉の問題』と記されている文書である。この文書の現物は、引用の形も含めて残っていないので、中身を知る手がかりは、略歴と次に紹介するレーニンの書簡で中身にふれた箇所から推測するほかにない。「党ペトログラード組織の欠陥なるものを強調、民主主義的自由の欠如がその原因であるとしてあらゆる政治的流派にたいする言論・出版の自由を要求」という略歴に記された箇所からいえることは、ミャスニコフが「あらゆる政治的流派」の「言論と出版の自由」を要求していたということである。21年といえば、レーニンが新経済計画(NEP)に踏み切った年であることも重要だ。内戦にかろうじて勝利したとはいえ、打倒の対象であるアメリカ経済の方法を採り入れないことには成り行かないほど国内経済は破綻をきたしており、党の腐敗も許し難い状態に陥っていた。このような背景があって、上に紹介した異例な書簡が書かれた。
③ 没年は不明――
レーニン死後の党内闘争は、トロツキーの除名(27年)と追放(29年)をもってスターリンの勝利が確定する。ソルジェーニツィンによれば千万の単位で逆流が始めるのは29~30年からだという。「労働者グループ」とは、いわゆる「労働者反対派」のことだが、この流れに巻き込まれたとすれば、ミャスニコフの没年が記されていない理由も納得できる。よほど高名でないかぎり、没年がわからないほど大量の人間が強制収容所で死んでいるからだ。
右に記したことを踏まえて、レーニンの書簡を見てみよう。少し長くなるが、この手記で私がふれたいと考えている核心と密接にからんでいるので、全文を引用する。
《同志ミャスニコフ!
やっときょう、あなたの論文を二つとも読みおえた。ペルム(ペルムだとおもうが)組織での君の発言がどんなものであり、この組織との衝突がどういう点にあるのか、私は知らない。これについてはなんとも言えない。この問題は、組織局がさばくであろう。組織局は、専門委員会をえらんだと聞いている。
私の任務はこれとは別なものである。それは、文献的および政治的文書としての君の手紙を評価することである。
興味ぶかい文書だ!
論文『焦眉の問題』は、私の見るところでは、あなたの根本的な誤りをとくにはっきりとしめしている。そこで私は、あらゆる手をつくしてあなたの説得につとめることを義務とみなす。
論文の冒頭で、あなたは弁証法を正しく適用している。そうだ、「国内戦」のスローガンと「国内平和」のスローガンとの交代を理解しないものは、こっけいである。それより悪くはないとしても。そうだ、この点ではあなたは正しい。
しかし、この点であなたが正しいからこそ、あなたが結論をくだすさいに、あなた自身の正しく適用した弁証法を忘れてしまったことに、私は奇異の感じがする。
……「帝政派から無政府主義者をふくめて、出版の自由を」……大いによろしい! しかし、失礼だが、すべてのマルクス主義者と、わが革命の四年間の経験について考えるすべての労働者は、言うであろう、どのような出版の自由か、なんのためにか、どの階級のためにか、考えてみようではないか、と。
われわれは「絶対者」というものを信じない。われわれは「純粋民主主義」を嘲笑する。
「出版の自由」というスローガンは、中世の終りから十九世紀までのあいだに、全世界的に偉大なものとなった。
なぜか? なぜなら、それが進歩的ブルジョアジーを、すなわち僧侶、国王、封建諸侯、地主にたいする彼らの闘争を表現していたからである。
大衆を僧侶と地主から解放するために、ロシア社会主義連邦ソヴェト共和国ほど多くの仕事をしたし、またしている国は、世界に一つもない。「出版の自由」というこの任務を、われわれは、世界のどの国よりもりっぱに遂行したし、また遂行しつつある。
資本家のいる全世界での出版の自由とは、ブルジョアジーのために、新聞を買いとり、執筆者を買いとり、「世論」を買収し、買いとり、製造する自由である。
これが事実である。
だれも、けっして、これを論駁はできないであろう。
だがわが国では? ブルジョアジーは撃破されたが、撃滅されてはいないこと、彼らが身をひそめていることを否定できるものがいるだろうか? これを否定することはできない。
世界のブルジョアジーという敵に取りかこまれたロシア社会主義連邦ソヴェト共和国内での出版の自由とは、ブルジョアジーとそのもっとも忠実な下僕であるメンシェヴィキおよびエス・エルとの、政治的組織の自由である。
これは、論駁できない事実である。
ブルジョアジー(全世界の)は、まだわれわれよりも強大であり、しかも何倍も強大である。このうえになお政治的組織の自由(=出版の自由。なぜなら出版物は政治的組織の中心であり、基礎であるから)という武器を彼らにあたえることは、敵の仕事をやりやすくし、階級敵を援助することを意味する。
われわれは自殺したくはないし、したがって、そういうことはしないであろう。
われわれはつぎのような事実をはっきりと見ている。それは、「出版の自由」が事実上、国際ブルジョアジーによる何百、何千のカデット、エス・エル、メンシェヴィキの著作家の即時買収と、彼らの宣伝、われわれにたいする彼らの闘争の組織とを意味するということである。
これは事実である。「彼ら」はわれわれより富裕であり、われわれの現有勢力に対抗して十倍も大きな「勢力」を買収している。
いや、われわれはそんなことはしないであろう。われわれは、世界のブルジョアジーをたすけるようなことはしないであろう。
どうしてあなたは、一般階級的な評価から、すなわちあらゆる階級間の諸関係の評価という見地から、感傷的・俗物的な評価に転落するようなことになったのであろうか? 私にはそれがわからない。
「国内平和か、国内戦か」という問題、われわれはどうして農民を獲得したか、また「獲得」しつづけている(プロレタリアートのがわへ)か、という問題、これら二つのもっとも重要な、根本的・世界的な(=世界政治の核心にふれる)問題(あなたの論文が二つともそれにあてられている)では、あなたは素町人的でない、感傷的でない、マルクス主義的な見地に立つことができた。そこではあなたは、あらゆる階級の相互関係を実務的に、冷静に、考慮することができたのである。
ところがここであなたは突然センチメンタリズムの深淵へ転落してしまった。
……「われわれのところには醜態と職権濫用が山とある。出版の自由はそれを暴露するであろう」……
二つの論文で判断しうるかぎり、あなたはまさにこの点で理路を失ったのである。あなたはいくつかの悲しむべき、苦い諸事実に押しつぶされて、冷静に力関係を評価する力を失ってしまった。
出版の自由は、世界ブルジョアジーの勢力をたすけるであろう。これは事実である。「出版の自由」は、ロシヤの共産党から幾多の弱点、誤り、不幸、病弊(病弊は山ほどあるということ、このことは論議の余地はない)一掃することには役だたないで――というのは、世界のブルジョアジーはそれをのぞんでいないから――むしろこの世界ブルジョアジーににぎられた武器となるであろう。彼らは死んではいない。彼らは生きている。彼らは隣接していて、機会をねらっている。彼らはすでにミリュコフをやとっており、チェルノフとマルトフは、(一部は愚かなために、一部はわれわれにたいする分派的憎悪のために、だが根本的には彼らの小ブルジョア民主主義的立場の客観的論理によって)「誠心誠意」このミリュコフに奉仕している。
あなたは「ある部屋に入ろうとして、別の部屋に入ってしまった」。
あなたは共産党を治療しようとおもったが、確実な死をもたらす――もちろんあなたからではなく、世界ブルジョアジー(+ミリュコフ+チェルノフ+マルトフ)から――ような薬をつかむことになったのである。
あなたはささいなことを、まったく取るにたりないささいなことをわすれてしまった、すなわち、世界ブルジョアジーと、新聞を買収し政治的組織の中心を買収する彼らの「自由」を、わすれてしまったのだ。
いや。われわれはこの道をすすまないであろう。一〇〇〇人の自覚ある労働者のうち、九〇〇人まではこの道をすすまないであろう。
われわれの病気はたくさんある。一九二〇年の秋と冬の燃料および食糧の分配のさいにおかしたような誤り(われわれの共通の誤り。労働国防会議も、人民委員会議も、中央委員会も、みな誤りをおかした)は、われわれの病状をさらに何倍にも激化させた。
窮乏と災害は大きい。
一九二一年の飢饉は、それをおそろしくつよめた。
それを切りぬけるには、言語に絶する苦労を伴うであろうが、しかしわれわれは切りぬけるであろう。またすでに、切りぬけはじめている。
われわれは切りぬけるであろう、というのは、われわれの政策は、あらゆる階級勢力を国際的規模で考慮した、正しい政策だからである。われわれは切りぬけるであろう、というのは、われわれは自分の状態を飾りたてはしないからである。われわれはすべての困難を承知しており、すべての病弊を見ている。われわれは恐慌に陥ることなく、それを系統的に、ねばりづよく、治療するであろう。
あなたは、あえて恐慌に夢中になり、この斜面を転落し、ついに、あなたによる新党の創立か、あなたの自殺に類する結果を生みだすにいたった。
恐慌に陥ってはならない。
党からの共産党細胞の遊離? それはある。これは害悪、不幸、病弊である。
それはある。重い病弊だ。
われわれは、それを見ている。
それの治療は、「自由」(ブルジョアジーのための)によってではなく、プロレタリア的・党的な手段によってすべきである。
あなたが経済の高揚について、「自動鋤」その他について、農民にたいする影響等々についてかたっていることは、多くの正しいこと、多くの有益なことをふくんでいる。
どうしてあなたはそれを強調しないのか? われわれは一致するであろうし、一つの党のなかで協力一致して括動するであろう。利益は莫大であろう。だがそれは、一挙にえられるのではなく、非常に緩慢にしかえられないであろう。
ソヴェトを括気づけ、非党員を引きいれ、党の活動を非党員に点検させる――これこそ、絶対に正しい。ここに山ほど仕事があり、無数の仕事がある。
なぜあなたは、実際的な方法でそれを発露させないのか? 大会のための小冊子のなかで?
どうしてそれに着手してはならないのか?
なぜ人足仕事(中央統制委員会を通じて、党の機関紙を通じて、『プラウダ』を通じて職権濫用に迫害をくわえるという)におびえるのか? 人足仕事、緩慢な、困難な、重苦しい仕事から、人々は恐慌に陥り、「容易な」打開策を、「出版の自由」(ブルジョアジーのための)を探しもとめる。
なぜあなたは、自分の誤りを、明白な誤りを、「出版の自由」というような非党的・反プロレタリア的スローガンを固執しなければならないのか? なぜあなたは、あまり「かがやかしく」(ブルジョア的な輝きによる)ない仕事、職権濫用の実際の一掃、それとの実際の闘争、非党員にたいする実際の援助といった人足仕事に手をつけてはいけないのか?
どこであなたは、これこれの職権濫用を中央委員会に指摘したか? また、それを訂正し、板絶するこれこれの手段を指摘したか? 一度もない。
ただの一度もない。
あなたは、おびただしい災厄と病弊を見いだし、絶望に陥り、そして他人の抱擁、ブルジョアジーの抱擁(ブルジョアジーのための「出版の自由」)に身を投じた。私が忠告したいのは、絶望と恐慌に陥らないようにということである。
わが国のわれわれに共鳴している人々、労働者と農民には、まだ底しれぬ力がある。健康はまだ多い。
非党員を抜擢せよ、党員の活動を非党員に点検させよ、というスローガンを、われわれはまだよく実行していない。
しかしわれわれはこの分野で、いまより百倍ものことをすることができるし、またするであろう。
あなたがすこし冷静に考えて、まちがった自尊心から、明白な政治的誤り(「出版の自由」)を固執するようなことがなく、気をしっかりもち、自分のなかの恐慌を克服して、非党員との結びつきをたすけ、党員の活動にたいする非党員の点検をたすけるという実際の活動に着手するものと、信じる。
この活動では、仕事は山ほどある。この活動でも病弊を、ゆっくりとではあるがしかしほんとうに治療することができる(またしなければならない)し、「出版の自由」によって、この「かがやかしい」鬼火によって、判断をくもらせてはならない。
共産主義者のあいさつをおくる。
レーニン》(『レーニン全集(第四版)』/大月書店/第32巻p541-547)
■この書簡をどう読むか
この書簡全体は、次に挙げる4つの姿勢に貫かれている。まずは、私が青字にした部分に注目していただきたい。
① 誠実かつ真摯な姿勢
所属をまちがえるほどの関係(ほとんど知らないということ)にあるミャスニコフという一古参党員に対して、「あらゆる手をつくしてあなたの説得につとめることを義務とみなす。」と書いている。これはきわめて異例なことだ。大ロシア帝国を継承した最高権力者が、無名の一党員を全力を挙げて「説得」するというのだから。
このような姿勢は、党内に蔓延する職権濫用について「病弊は山ほどあるということ、このことは論議の余地はない」と認めているところにも見ることができる。
② 組織の腐敗は部外者の監視によってしか正せないとする姿勢
組織における腐敗は、外からの監視によってしか正せないことについても、これを認めている。「非党員を引きいれ、党の活動を非党員に点検させる――これこそ、絶対に正しい。」「非党員を抜擢せよ、党員の活動を非党員に点検させよ、というスローガンを、われわれはまだよく実行していない。」とする姿勢である。
③ 金さえあればなんでも買えるとする姿勢
その一方で、金さえあればなんでも買えるとする姿勢に貫かれている。逆にいえば、人は魂を金で売るものだとする観念に凝り固まっている。
④ 階級を絶対視する姿勢
この姿勢は、階級間には越えられない絶対的な溝があるとする宗教的信念にまで高められている。このことは「われわれは『純粋民主主義』を嘲笑する。」ということばに、象徴的に表現されている。
①と②についていば、これほど誠実かつ真摯な姿勢を示した権力者は、私が知るかぎりではレーニンしかいない。同じように③と④に見られる硬直した姿勢は、ルターのような宗教家には見られるが、超一流の政治家にあっては滅多に見られないものではない。私たちは、レーニンを政治家として見ることを前提にしてきた(事実、政治家であったことに疑いの余地はない)が、宗教家として見直してみると、いままでは見えなかったこの人物の真実の姿が見えてくるのではないか、と私は思うのだ。高潔さと謙虚な姿勢において図抜けている一方で、他方では度し難いほどの思い込みと人間に対する無理解が共存しているという点でいえば、レーニンとルターは、同じタイプの人物だと思うからだ。
■重なるもの
私は、この書簡の存在を、70年の10月に、未決で拘留されていた東京拘置所の独居房で知った。私がいた舎房には、4・28闘争で破防法が適用され、被告人とされた本多さんが先住者としており、面会のさいに顔を合わせ、目で挨拶を交わすという関係にあった。
前年の10・21闘争を前にして、逮捕・起訴を覚悟していた私は、獄中で読むべき本の1つをレーニン全集と決め、神田の古本屋で買い求めていた。私が買った4版は35巻、定価1000円でだったので、当時の私には懐具合を考えると手が出なかったが、たまたま5冊ほど欠本があるものがあり、それは全巻揃いのものに比べて半値以下だったので買ったのである(それでもかなりの出費だったが)。10・8羽田以降の闘争の高揚は、革命の「現実性」を示していた(と私たちには感じられた)。69年に入って、街頭蜂起の方針が出されたときには、「いよいよ時がきた」というのが、私たちが共通に抱いた素直な感懐だった。
読み始めたのは起訴後の11月に入ってから。ほぼ1年かけ、全巻(といっても先にふれたように欠本があり、34巻と35巻はなかった)を読破する直前になって、この書簡に出合ったのである。
全集の読破は退屈な作業だった。マルクスやエンゲルス、トロツキーなどが書いたものは理念にかかわるものが多い。いってみれば観念の世界を展開している。それらとは異なり、レーニンが書いたものは、とくに権力奪取後に書かれたものは、実務にかかわるものが過半が占めている。実務家ならいざ知らず、読んでいておもしろいものではない。それでも、実務に取り組むレーニンの姿勢に、私は鬼気迫るものを感じていた。なかでも、内戦後の食糧危機にさいして、確保した食糧と人口構成の数値を前にして、1人当たりの配給量をいかにすべきかを検討するレーニンの姿勢には、感動をおぼえるものがあった。「あるべき政治家」の姿を、私は、レーニンのなかに読み取っていた。爆発寸前の危機的状態にある条件下にあって、公平性を保ちながら、なおかつ、労働生産性を刺激することも考慮しなければならないこの作業は、相矛盾する難問題を含んでいる。どちらか一方に傾いても、不満が爆発しかねない。年齢と性別に分けられた表を前にして、レーニンは、そこに書き込むべき数値を決めるのに全精力を注いでいた。なぜその数値にしたかについての説明に苦慮していた。その姿勢に感動をおぼえたのである。
そういうときに出合ったのが、この書簡である。一地方活動家の反抗が、いちいち最高指導者に耳に入ることなど、一般的にいって考えられることではない。なにかの回路をたどって伝わったとしても、普通なら然るべき下僚に委ねるべき性格のものだ。そういう類の問題に過ぎないミャスニコフの問題提起に対して、「あらゆる手をつくしてあなたの説得につとめることを義務とみなす。」と断言するレーニンに、私は、本多さんと自分との関係を重ねて読んでいたのである。
小野田の指摘を受けて、この書簡を読み直して、改めてミャスニコフという一無名活動家とレーニンとの関係に、私と本多さんと重ねていたことに思い至った。あわせていえば、このことは、全ての原理主義に通底すると思った。ひとりのカリスマ指導者とその指導者に対して全的に信頼を寄せる組織成員との関係は、その組織が必ずしも宗教組織でなくてもいえることだが、疑念を入り込ませない関係になりがちである。それが宗教組織になると、より疑念が入り込む余地は狭まらざるを得ない関係になる。そういう宗教組織にあっては、外から見ると絶対的な従属関係にしか映らないものにもかかわらず、当事者のあいだでは純粋に「精神の問題」でしかないのだ。
本多延嘉の邂逅と別れから、はや30年の歳月が経た。このあたりで私なりの決別をしないことには、「全体小説を書く」などと偉そうなことをほざいたところ始まるまい――いま、そういう心情の下に、私はいる。
2005・2・26
06/4月号 今月の断章
観念としての暴力革命論がある。人はこれを理念とするとき、その観念は信仰に一歩近づく。さらに一歩進んでそれを己の政治課題に据えたとき、それは信仰になる。
宗教は、その信者を獲得するために傘下の信者がもてる全てを動員することを常とする。ときには全てを捧げることを要求する。このことはキリスト教文明を見れば明らかだ。現代最大の宗教だったマルクス主義が隆盛を誇り得たゆえんもここにあった。通信手段がそれ以前の時代と比べて飛躍的に発達を遂げた時代だっただけに、その効果は絶大だった。他の大宗教が何世紀もかけておこなったことを、わずか百年余の時間をかけただけで実現し得たのである。近代に固有のこの伝搬力は、宗教としてのマルクス主義においては最大の武器だっただけに、その武器は破綻をもたらす力としても働くことになった。人間の歴史が愚かさと賢さが複雑に入り交じった時間の連続であることを考えれば、このこともまた歴史の必然だといえる。 2006・3・25
〈編集ノート〉06.4月号
★西部との付き合いを終えてひと息つき、これでいよいよ〈本来の戦線〉に復帰できると考え、その準備を始めた。そんなおり、またまたひょんなことから今度は小野田襄二と付き合う羽目になった。なぜ、そうなったのかを含めて「ある元過激派の手記」(仮題)で書くことにした。詳しくはそちらを読んで貰うとして、ここでは1つだけふれておく。
私の課題は、この国において受け継がれてきた〈受け継がれるべき精神〉のあり方を、自分が生きた時代とのからみで残すことにある。そのための方法はいろいろある。得手不得手ということもあるが、私は小説の形で書くことを選び、その手始めにと思って書いたのが『序章』である。4半世紀前ことである。当然のことながら、序章につづく第2章を書くことが、それからあとの課題だった。このホームページに掲載したものは、高校生のおりに書いた最初期の小説を除いて全てそのための準備過程の産物であり、序章につづく第1章の荒稿が「試作」欄に掲載してある「光りと陰」である。
☆西部との付き合いを終えて、その準備に関しては一段落したと思った。だから、前号では「『光と陰』の続稿を、冒頭の部分だけでも掲載できるようにしたいと思っている。」と書いた。ところが、ひょんなことから古い友人から小野田の著作を指摘され、参考までにと目を通した結果、もっとも肝心なことが抜け落ちていたことを知らされた。ひとことでいえば、私の検証が観念の世界に偏っており、生身の人間が生きる(生きてきた)現実に対して目を向けてこなかったということである。弘法も筆を誤るのが人間の世界である。間違いに気づいても、行きがかりから途中で修正できないのが人間の当為である。そうした〈性〉の部分、別言すれば、人間の闇の部分との格闘を抜きにした小説の世界が人の琴線に響くはずがない。よくいっても表層にふれる程度で終わりである。その程度のものなら、掃いて捨てるほどあるわけで、いまさら私が書かねばならないいわれはない。小野田の著作にふれて、そのことを痛感させられたのである。
★今シーズンはワセダが健闘してくれたので、久しぶりに溜飲が下がる思いをした。私と同じ感懐を抱いたファンは多いはずだ。日本では社会人といっているが、あれは歴としたプロである。アマチュアがプロに敵うはずがないわけで、ワセダの完敗、東芝の完勝は予想されたことではあった。だから、来シーズンも同じようになるにちがいない。が、それでも学生がプロに挑戦しつづけるところに、このスポーツの醍醐味がある。負傷で交代を命じられた1年生の豊田が悔し泣きをしている姿、同様に交代した4年の首藤がヘッドキャップを取って競技場に向かって深く一礼する姿が印象に残ったシーズンだった。
☆『福澤諭吉の真相』の著者である平山洋さんから、前号で書いた私の書評に事実誤認があるとのメールを貰った。訂正も含めて、参考資料を別掲した。前号の書評を補強する意味でも、目を通していただければ幸いである。
★西部のときと同様に、今号も無手勝流で臨んだ。これが私流のやり方なのだから、仕方ない。問題だったのは、西部のときと比べても今回は格段と準備不足であることだ。だから、形をつけるのに四苦八苦した。なんとか予定日までにあげようと頑張っが1日延びてしまい、中身もよくない。この取り返しは次号ですることで勘弁して貰うほかにない。
2006・3・・25
| 2700円+税 |
| 2018年10月2日 |
| 四六判並製 |
| 368頁 |
| ISBN978-4-7845-9223-4 |
| C0030 |